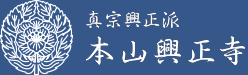【二百七十七】学林 その三 学林の講義
2025.01.25
西本願寺の学寮は、幕府の許可のもと、元禄八年(一六五五)四月、学林と名を変え、正式に再興されます。
学林が四月に再興されたのは、学林での講義が四月十五日から始まるためです。学林での講義は四月十五日から六月十五日までの夏季九十日間にわたって行なわれるのが原則です。いわゆる安居の制に倣って、この期間に行なわれるのです。学林ではここから講義の行なわれる九十日間を夏中といい、講義の終了後から翌年の講義の開始までの期間を夏間といっていました。もっとも、この学林での六月十五日までの講義というのはあくまで原則であって、実際にはこれより何日も早くに終了することもありましたし、逆にこれよりも何日も遅くまで講義を続けたこともありました。さらには四月十五日という講義の始まる日でさえ、ずれることもありました。この夏の講義のほか、秋には秋講、冬には冬講、春には春講といわれる講義も行なわれましたが、これらは必ず行なわれるというものではなく、必要に応じて行なわれるものでした。秋講、冬講、春講は夏の講義に比べ、期間も短く、受講者も少なめでした。
江戸時代には西本願寺だけではなく、仏教の各宗派で、檀林や談義所といった僧侶の教育機関が設けられていきましたが、それらの僧侶の教育機関でも安居の制に従って夏に講義が行なわれていました。
末寺僧侶の子弟は学林に入り、所化として講義を受けますが、この学林に入り、学林に籍を置くことを懸籍といいます。そして、翌年、さらに所化として学林に籍を置くことを続籍といいました。通常、所化は学林の寮に住み、講義を受けます。学林に入り、所化を続けるには、入寺銀という経費を納める必要がありました。学林の講義は夏季九十日間にわたって行なわれましたが、学林に一年、懸籍し、夏の講義を受けた場合、これを一夏と数えました。二年なら、二夏です。西本願寺の派内の取り決めでは、末寺の住職になるには基本的に三年以上、学林に在籍しなければならないとされていました。しかし、そうはいっても、遠隔地の寺や貧困な寺の子弟にとって、三年も京都の学林に在籍するというのは困難なことです。この三年以上、学林に在籍するというのは建前上のことであり、三年以上、学林に在籍することのないまま住職になった者も大勢いました。
学寮が学林と名を変え、正式に再興された元禄八年の夏の講義の講師をつとめたのは、京都の六条大宮にある光隆寺の住持であった知空です。
月再興学黌於東中筋、四月成、十九日知空講楞厳経於新黌(『大谷本願寺通紀』)
元禄八年二月、西本願寺の門前の東中筋の地で学林の再興の工事が始まり、四月にそれが完成し、四月の十九日から知空が新しい学林の建物で楞厳経を講じたとあります。学林での最初の夏の講義から安居の結制の日である四月十五日より四日遅れて講義が始まっています。
この学林での最初の講義の講師をつとめた知空は、この時代の西本願寺の門下の僧たちを代表する学匠です。学林が正式に再興される以前、学林のあった地には医者の挙屋敷があり、そこが仮の学林として用いられていました。その仮の学林では三人の能化の代役が順次に講義を行なっていましたが、知空も能化の代役の一人として仮の学林で講義を行なっていました。正式に再興された学林でも知空は引き続き講義を行なっているのですが、講義を行なっているからといって、知空は能化になったわけではありません。知空は初代の西吟に次いで二代目の能化になりますが、知空が能化になるのは、これからかなりのちのことです。
知空は京都の粟田口の真覚寺に生まれ、十九歳の時、西本願寺の御堂衆になります。光隆寺は知空自身が開いた寺で、知空が二十七歳の時に開いたものです。学林が再興された時、知空は六十二歳でした。
知空は御堂衆でしたが、この時代には御堂衆の中に学問に優れた僧が多くいました。仮の学林では、途中の交代もあって、知空を含め計六人が能化の代役となっていますが、この六人は、皆、御堂衆です。これは学林がまだ仮のものであったことから、西本願寺が御堂衆に講義を行なわせたのだとみられますが、それらの御堂衆は実際に学問に優れていたのだと思います。御堂衆は御堂での勤行や内陣での給仕にあたりますが、経論や故実にも通じる必要がありました。そのため学問を積まなければならなかったのです。
(熊野恒陽 記)