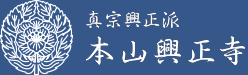【二百八十】仏護寺十二坊 その二 寺内宗旨判形帖
2025.04.24
広島藩は、元禄十四年(一七〇一)、広島の町での宗門改めのやり方を部分的に変更します。広島城下では、寺が召し使っている男女の者たちの宗門改めについては、まずその召し使われているそれぞれの男女の旦那寺がそれらの男女が自分の寺の檀家の者であるということを明示した証文を出し、その証文をこれらの男女を召し使っている寺が集めて、それを帳面にまとめた上、男女を召し使っている寺の住持がそこに判形を据えて藩に提出していました。この住持の判形を据えた帳面を寺内宗旨判形帖、といいました。元禄十四年の変更ではこの寺内宗旨判形帖による宗門改めそのものには変更はありませんでした。しかし、塔頭寺院については、変更がありました。塔頭寺院の場合は、それまでは塔頭の住持が判形を据えるとともに塔頭が属する本坊の住持も判形を据えていましたが、元禄十四年からは塔頭の住持は判形を据えずに、本坊の住持のみが判形を据えるように変更になったのです。
仏護寺と仏護寺十二坊は元禄十四年から激しく対立することになりますが、その直接の契機となったのはこの広島藩の宗門改めの方法の変更ということです。
仏護寺と仏護寺十二坊は、元来、それぞれ別の場所にあったのだと伝えられています。それを広島城の築城と城下町の整備を進めていた毛利輝元が文禄二年(一五九三)ころ、いまの本願寺の広島別院のある寺町の地よりさらに西の小河内という地の付近に移転させます。これで仏護寺と十二坊は一箇所の地に集められたのです。その後、仏護寺と十二坊は慶長十四年(一六〇九)に福正則によって、いまの寺町の地に移されます。江戸時代の仏護寺と十二坊のあった寺地は大きなもので、その規模は南北三町半余、東西一町余と記録されています。一町は六十間です。この寺地は寺内町のようなものであって、ここには寺だけではなく、多くの町家も建っていました。時代により変化もありますが、江戸時代の終わりのころには六十四戸の町家がありました。寺地の中には南北に道が通されていて、寺地は道により東西に大きく二分されていました。仏護寺はその寺地の東側の地の北の端にありました。仏護寺の直接の境内地は道に面した南北が六十間、奥行にあたる東西が三十間の広さです。奥行といっても、仏護寺の本堂、門は南向きに建てられており、道から、一旦、東に入った所に門がありました。
道の東側には仏護寺から南に向かって、順に蓮光寺、光福寺、徳応寺、光円寺、真行寺、報専坊の境内地がありました。十二坊のうちの六つの寺です。この六箇寺に対応するかたちで、道の反対の西側には南に向かって、順に光禅寺、善正寺、円竜寺、正善坊、元成寺、専福寺の境内地がありました。こちらも十二坊のうちの六つの寺です。専福寺はのちに寺号を改めて、超専寺となります。十二坊の境内地は道に面する間口が二十間、奥行が三十間で、十二坊とも同一の広さです。仏護寺の境内地が千八百坪で、十二坊の境内地がそれぞれ六百坪となりますが、これは仏護寺は本寺として十二坊の上にあるとともに、十二坊はそれぞれ同格であるということを示しています。この十二坊の所在する場所は時代とともに変わっていき、東側の南にあった報専坊はのち西側の光禅寺の北側に移り、東側の北にあった蓮光寺も光禅寺の北側に移った報専坊のさらに北側に移ります。そして、その北側には仏護寺の下人の家を挟んで品窮寺が境内地を有するに至ります。品窮寺も十二坊の一つです。仏護寺十二坊は十二坊といいつつも実際には十四箇寺あります。このほかには正伝寺が十二坊の寺ですが、この正伝寺は寺町の地には移転しませんでした。正伝寺以外にも、十二坊の寺のなかには、寺町には境内地だけがあり、寺そのものは別の地にあるという寺もありました。
このほかの大きな変化としてあげられるのは、東側の光福寺と徳応寺の間に割り込むようなかたちで浄専寺が境内地を有することになったことです。浄専寺の境内地も二十間に三十間で十二坊と同じ大きさです。しかし、この浄専寺は十二坊ではありません。東側の南にあった報専坊が西側に移っていることからするなら、徳応寺の境内地が浄専寺の境内地となり、以下、順に一つずつ南側に移ったようにも思われます。
十二坊は意図的に一箇所に集められたものであり、仏護寺の塔頭ではありません。ところが、広島藩は十二坊を仏護寺の塔頭とみていました。藩は十二坊の召し使っている者たちの寺内宗旨判形帖には仏護寺だけが判形を据えるよう命じてきたのです。
(熊野恒陽 記)