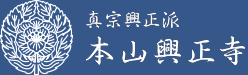【二百八十四】仏護寺十二坊 その六 判形を据えることを許される
2025.08.25
興正寺が広島藩と交渉したことにより、町の大年寄の家屋に預け置きになっていた仏護寺十二坊のうちの三箇寺の住持や、閉門になっていたほかの十二坊は罪を許されました。元禄十五年(一七〇二)の春のことです。この時、罪を許されたのは十二坊だけではありませんでした。仏護寺の末寺である浄専寺も閉門を許されました。浄専寺も十二坊とともに仏護寺の塔頭とされ、塔頭ということで寺内宗旨判形帖に判形を据えることができなくなりました。そのため十二坊とともに、藩にこれまでと同じく判形を据えることにしてもらいたいと求めたことから、十二坊と同様に閉門ということにされていました。浄専寺は寺町ではほかの十二坊の寺と並んで建っており、境内地の規模も六百坪とほかの十二坊と同じ規模でした。ここからすると、浄専寺は仏護寺の門下では十二坊と並ぶ待遇をうけていたということになります。仏護寺はもともと佐東郡の金山の山麓の龍原にあったと伝えられますが、浄専寺はその時代から仏護寺に仕えていた末寺なのだといいます。龍原にあった時には、浄専寺は上坊(うえのぼう)といわれていたとされ、江戸時代にも一般にはそのまま上坊といわれていたのだとされています。
上坊といふあり、即寺内浄専寺にして、今も世に上坊と唱ふ(『知新集』)
古くからの末寺ということで、別格に扱われていたのです。しかし、この浄専寺は十二坊ではありません。広島藩も十二坊と浄専寺を区別して扱っていました。
興正寺の要望の通りに、十二坊、浄専寺は罪を許されましたが、興正寺が藩に要望したのはこれだけではありませんでした。興正寺は、十二坊と浄専寺の住持が寺内宗旨判形帖に判形を据えることができるようしてもらいたい、ということも要望していました。しかし、藩は判形を据えるということは許しませんでした。
正恩寺へも寺社御奉行あひ、十二坊閉門ゆるしやりぬ、判形の事ハえもゆるさすよしいふ、其後、正恩寺、帰京せり(『知新集』)
広島藩の寺社奉行は興正寺の使僧、正恩寺に会い、十二坊の閉門などのことは許すが、判形のことは決して許さないといったのだとあります。仕方なく、正恩寺は京都に戻りました。
元禄十五年の春には、広島藩の藩主、浅野綱長が参勤のため、江戸に向かうということがありました。一行は船で江戸に向かっており、その船は大坂に着船することになっていました。興正寺はこの機を捉え、正恩寺を大坂に遣わし、一行に、再度、判形を据えることができるようにしてもらいたいということを伝えました。しかし、この時にも、興正寺の要望は受け入れてもらえませんでした。興正寺の申し入れは続きます。元禄十五年の八月、今度は藩主、綱長のいる江戸に正恩寺を遣わします。そして、ついに判形を据えることが許されることになったのです。
判形の事、あなかちに御頼ありけるゆゑ、やうやく寺内宗旨判形帖の連判ゆるさるへしとの御評議にきハまり(『知新集』)
興正寺があまりにも執拗に申し入れを続けるので許したのだとあります。興正寺が執拗に申し入れを続けたのは、本寺として末寺である十二坊、浄専寺を助けるためですが、それとともに十二坊を塔頭とする藩の捉え方が誤りであると分かっていたため、興正寺は申し入れを続けたのでした。
判形のことを許されたのち、正恩寺は京都に戻ると、すぐに京都から広島へと向かいました。そして、九月四日、正恩寺は仏護寺に仏護寺の住持と十二坊の住持たち、それに藩が寺内宗旨判形帖に塔頭の住持は判形を据えずに本坊の住持だけが判形を据えるように命じた際、これに逆らった十二坊の住持たちの説得にあたった明教寺の住持を集めて、藩の寺社奉行から仏護寺と明教寺の両寺に宛てた口上書と、仏護寺だけに宛てた口上書の二通を伝達し、今後の寺内宗旨判形帖の判形についての方針を説き聞かせました。
当年より連判被仰付候、仏護寺境内之儀ハ、先規通、相違無之(『知新集』)
寺社奉行から仏護寺に宛てられた口上書の一部です。寺内宗旨判形帖には十二坊と仏護寺の住持の両方が判形を据えるようにするとあります。十二坊の住持たちも判形を据えることができるようになったのです。ただ、それに加え、十二坊が仏護寺の境内に建っているということはこれまでいってきた通りだともあります。十二坊は仏護寺の塔頭だというのです。
(熊野恒陽 記)